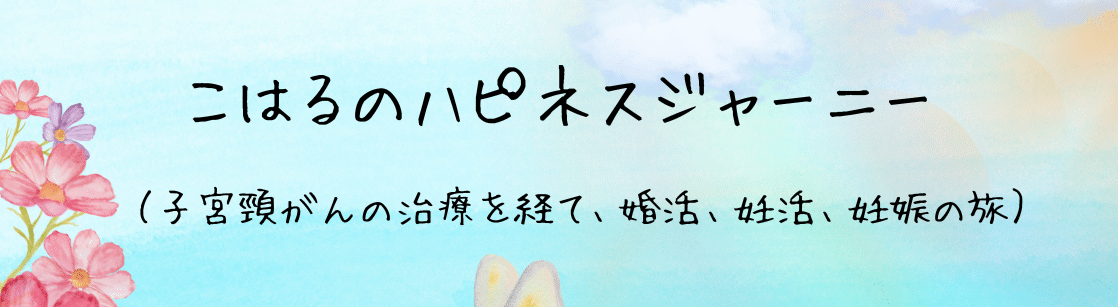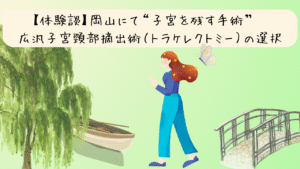広汎子宮頸部摘出術(トラケレクトミー)は、妊娠の可能性を残したい患者さんのために行われる手術です。
私も「子宮を全て摘出するか、残すか」という選択を迫られ、この手術を選びました。
説明を受けたとき、想像していたよりもずっと複雑で精密な手術だと知り、改めて医療のすごさを感じました。
どんな手術なのか、説明を受けてわかったこと
手術では、骨盤リンパ節郭清という、リンパ節を一緒に切除する処置も行われます。
これは、がんがリンパに転移していないかを確認するために必要な工程だそうです。
私が受けたのは「ロボット支援下腹腔鏡下手術」という方法。
お腹に小さな穴を開け、炭酸ガスを注入して空間を作り、立体的な映像を見ながらロボットを遠隔操作して行う手術です。
医師の手の動きを精密に再現できるため、より繊細な操作が可能になります。
腹腔鏡下手術のメリットと注意点
説明を受けて驚いたのは、腹腔鏡下手術にはさまざまなメリットがあるということ。
たとえば――
- 傷口が小さく、回復が早い
- 術後の痛みが軽減される
- 食事や歩行の開始が早い
- 出血量が少ない
ただし、まだ十分なデータの蓄積がないため、国内では標準治療ではなく「先進医療」にあたります。
そのため、自費負担が必要になると説明されました。(ブログを書いた2025年時点でも自費負担のようです。)
正直なところ費用面の不安はありましたが、命に代えられるものはないと思いました。
手術の流れ
手術中は、お腹の中に炭酸ガスを入れて視野を確保し、
骨盤リンパ節や子宮頸部の靭帯を切除していきます。
摘出した組織は膣から取り出され、残った子宮と膣を縫い合わせて閉じます。
さらに、妊娠中の早産を防ぐために、子宮頸部を縫い縮める処置(縫縮)も行われます。
この「縫縮」は、妊娠時に早産を予防するための大切な処置で、
のちに私が妊娠した際、追加の縫縮術を受ける必要がなかったのは、まさにこの時の手術のおかげでした。
合併症やリスクについて
説明の中では、いくつかのリスクについても詳しく話がありました。
- 出血や感染、血栓症
- 尿管・膀胱・腸などの損傷の可能性
- 排尿障害(膀胱麻痺や尿意の低下)
- リンパ浮腫や創ヘルニア
私自身も、術後しばらくは尿意がわかりづらく、自己導尿を1か月ほど行っていました。
夜中に失敗してしまうこともあり、最初の頃はかなり戸惑いました。
また、リンパ浮腫の症状も1~2か月ほど経ってから出てきました。
鼠径部や下腹部がむくみ、きつめの下着をつけると余計につらく感じることも。
鼠経の締め付けが少ない、「Sheepeace(シーピース)」というブランドの下着を愛用していました。大変助かりました!
術後の妊娠について
当時の資料によると、2020年当時の妊娠率は約57%。
そのうちの約半数は不妊治療による妊娠でした。
また、妊娠できても流産や早産のリスクが高く、
実際に出産に至ったケースでも、早産によってお子さんに後遺症が残る場合もあるとのことでした。
それでも私は、「今できる最善の選択をしよう」と思えたのを覚えています。
ロボット手術と聞いて少し不安になったけれど、
「なるようになる」と自分に言い聞かせ、前に進む決意を固めました。
次回は、実際の手術当日から入院生活、退院後の経過について書いていきます。
同じように悩んでいる誰かの参考になれば嬉しいです。